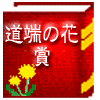 |
第1回 Short Story FIGHT CLUB 「道端の花賞」受賞作品 |
[道端文庫へ] |
| 第一回FIGHT/テーマ「新」 | ||
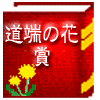 |
第1回 Short Story FIGHT CLUB 「道端の花賞」受賞作品 |
[道端文庫へ] |
| 第一回FIGHT/テーマ「新」 | ||
「新しい趣向」
作者・ライボス
家内とこういうところへ来るのは初めてだ。町の小さな演芸場。やっているのは『ショートショート朗読の夕べ』だ。これは新しい趣向に違いない。少なくとも、今まで一度もそんなのは聞いたことがない。
「あなた、もう出ましょうよ。なんか、次から次と見たこともない人が出てきて、原稿読んでは帰って行くだけじゃないの。内容もちっとも面白くないし」
家内には、コントとショートショートの区別もつかないし、顔も名前も知らないアマチュア作家ばかりが出ているので退屈するのも無理はない。
「まあ、待て。次はヘップバーンだから」
「ヘップバーン?なによそれ?」
「いや、おおとりって意味だよ。業界じゃそういうらしいよ」
「また、いいかげんなこと言って。あなたのおやじギャグにはうんざりだわ」
「そう言うな。ほら、始まったぞ」
幕が開き、白衣の若者が登場した。
「新発見!」
若者は、大きな声でタイトルを読み上げてから、朗読にうつった。
*****
午後のティータイム。自販機でカップコーヒーを買って研究室に戻った僕を、いつの間にか戻ってきていた博士が笑顔で迎えてくれた。
こういうのは何か、具にもつかないことを思いついた時だ。僕のコーヒーを見てから、急ににこやかになったのも気になる。
「キミ、遅いじゃないか!わしの新発見を見せてやろうと思って待っておったんじゃよ」
ほらきた。昔なら、目を輝かせて受け答えをしていただろうが、今はそんな気にもならない。
「あ、いらしてたんですか。もう今日は、来られないかと思ってました。で、新発見てのはなんです。私、それほどヒマでもないんですけど」
コーヒーが自分の分しかないのは、あんたが来ないと思ったからだとの説明も兼ねて、僕は言った。
「うむ、実は煙草を喋らせる方法を発見したんじゃ」
ヘビースモーカーである博士は、そう言って新しい煙草に火をつけた。
「煙草が喋る?まさか…。あの、自分の研究続けていいでしょうか?」
また、とんでもないことを言い出したものである。
「まあ、時間はかからんから見ておれ。それじゃあ、カウントダウンを始めるぞ」
「はいはい、勝手にやってください」
「一」
「二」
「三」
「カウントダウンじゃなくてアップしてるじゃないですか」
「ええい、だまって見ておれ」
「四」
「五」
「六」
「どこまで数えるんですか?」
「だまっておれというのに。もうすぐじゃ」
「七」
「八」
「九.よし、今じゃ!」
そう言うと、博士は僕のコーヒーカップに火のついた煙草を落とし込んだ。
――じゅう。
*****
若者は、朗読を終えると、深々と礼をし去っていった。
「どう?面白かった?」
帰り道、寂れた商店街を歩きながら、家内に問い掛けた。
「ぜんぜん。なにが『じゅう』よ。あんなのに、お金を払うなんて、すごく損した感じ」
家内はむくれている。僕だけが笑いころげたのも気に入らなかったようだ。
「お金?そんなもん払っちゃいないさ。ほら、年末に、商店街の抽選会でペアチケットが当たっただろ。あれで入ったんだよ」
家内の足が止まった。
「うそー!あれって、この商店街のホールならどこでも使えるってやつでしょ、映画でもコンサートでも。なんで、あんなしょうもない出し物に使っちゃうのよ」
「そう言うなよ。映画ったって、こんな寂れた街じゃ、名作劇場とか言って、おそろしく古い映画の三本立てをやってる程度だし、コンサートにしても、テレビに出られなくなったオチこぼれ歌手が来るぐらいじゃないか。それになにより、あの抽選券は僕の靴の裏のチューインガムが拾ったということを忘れてないか?」
「拾った券でも、当てたのはこの私よ。あーもったいない。せっかく、タダで見られるチャンスだったのに」
「だからこそ、おまえと何か新しい物を見るために使いたかったんだよ」
「なんでよ?」
「だって、昔から『女房とタダ見は、新しい方がいい』って言うじゃないか」
「ばか!」
<了>
あとがき =この作品の「新」とは 1.タイトルに新がついてる(^^ゞ 2.合法的にSS二作品を投稿している 3.新で落としている 4.文中のSSタイトルにも新がつく(^^ゞ 5.作品自体が新しい趣向である(自己評価)
[道端文庫へ]